
 人事コラム
人事コラム

労務コラム2025.07.11【徹底解説】 健康経営優良法人2026認定制度の申請ガイドとスケジュール解説!

労務コラム2024.11.29採用の「成功」と人材「定着」のために不可欠なオンボーディング施策の真価

労務コラム2024.08.09今さら聞けないBPRとBPOの違い~人事BPRのメリットと進め方を徹底解説~

労務コラム2024.07.25健康経営優良法人の申請に向けた公開座談会!経営と現場、各ポジションの申請の壁と解決のヒント
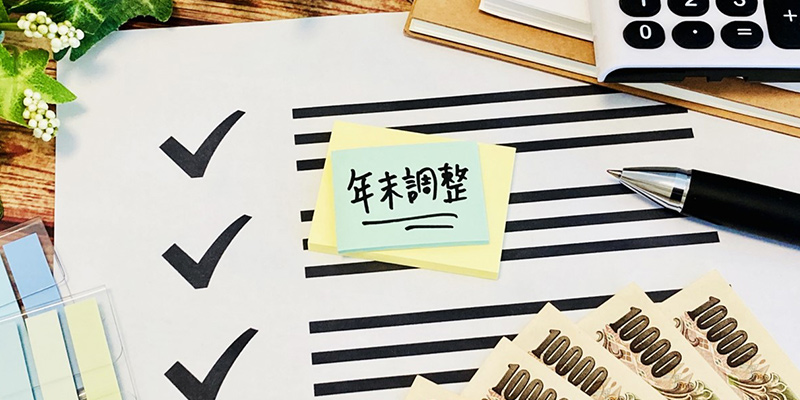
労務コラム2024.07.04年末調整のストレスから解放される方法! アウトソーシングの活用術

労務コラム2024.06.10離職防止のカギはここにあり! いますぐ企業が取り組むべき定着率向上施策

労務コラム2024.05.16定額減税(令和6年)事業者の対応とQ&A 海外赴任者はどうする?

労務コラム2024.04.25なぜ、いま人事BPRが求められているのか?
人的資本経営を支える人事BPRトレンド4選

労務コラム2024.03.14日本のGDP世界4位に転落!世界ランキングから見る労働生産性を低下させる要因をチェック

労務コラム2024.03.07健康経営の事例2社から学ぶ「健康経営の実践のポイント」

労務コラム2024.01.22健康経営アドバイザー資格取得に向けて“初めに覚えておきたい”健康経営の専門用語4選

労務コラム2024.01.18セミナーレポート:SDG’s week EXPO(日経メッセ)
持続可能な組織づくり「働きがいと成長」を両立する健康経営の最新事例

労務コラム2023.12.07証明書の様式標準化と効率化

労務コラム2023.11.135分でチェック! 2024年以降の法改正情報

労務コラム2023.09.07人事・労務担当者のための情報管理とセキュリティ意識向上の取り組み

労務コラム2023.08.09超実用的!人事データの可視化6つの手順

労務コラム2023.07.06どうする?年末調整 2023年版 夏本番の前に押さえておきたい!年末調整2つの改定ポイント <2023年度版>

労務コラム2023.05.30人事DXのカギを解説「捨てること」ではかどる業務改革

労務コラム2023.05.10何から始める?人的資本経営5つの基本で進める情報開示

労務コラム2023.04.10忙しい労務ご担当者様に送る!【2023年】労務関連法改正まとめ

労務コラム2023.01.18セミナーレポート
人的資本経営のレポーティングと、データのポイントとは

労務コラム2022.07.26関心を持つことでちょっとした変化に気が付く! メンバーマネジメントの3つのポイント

労務コラム2022.06.23その給与計算ベンダーの導入効果は継続できていますか? ナレッジ・ノウハウの空洞化問題は大丈夫?

労務コラム2022.05.19これまでの給与計算などの業務フローを踏襲しないでリプレイス? 最適なソリューションを検討!

労務コラム2022.04.14給与計算担当者はエッセンシャルワーカー!? コロナ禍だから実現した人事・労務のDX進化

労務コラム2022.03.10当社だから実現できる採用支援と人事労務支援のコラボレーション

労務コラム2022.02.16人事施策充実化の落とし穴「その仕事、持続可能ですか?」 労務業務見直しのすゝめ

労務コラム2021.12.01忙しい労務ご担当者様に送る!【2022年】労務関連法改正まとめ

労務コラム2021.11.02Withコロナによる新しい働き方、変わる手当

労務コラム2021.07.01生産性を高める年末調整運用スキーム 2021年版! ~電子化活用のススメ~

労務コラム2021.06.11新時代に突入した今だからこそ検討したい「人事部に残すべき業務」とは

労務コラム2021.04.23給与計算をアウトソースしても業務が減らない人に教える チャットボット導入によるヘルプデスクサービス

労務コラム2021.02.25業務効率化を図りたい方に知ってもらいたい「工数管理」のポイント

労務コラム2021.01.28【男性育休義務化】今のうちから人事部が備えておくべきこととは? (育休取得社員のリアルな声)

労務コラム2020.09.30セミナーレポート
リモート環境下における「人事DX」をどう進めるか?

労務コラム2020.08.24HRテックの戦国時代! 群雄割拠の社内システムを導入・運用する為に検討すべきこと

労務コラム2020.06.22タレントマネジメントで見落とされがちな「鮮度」と「精度」

労務コラム2020.04.20定量的にアウトソースの投資対効果を考えるうえで 見落としがちな「みえないコスト」

労務コラム2019.12.25給与計算の間違いが多い担当とその上司が知るべき「ミスを誘発する4つの要因」と解決策

労務コラム2019.09.20なぜ!? 元の業務フローに回帰する改善後プロセスの怪奇

労務コラム2019.06.12なぜアウトソーシングを活かしきれないのか? 人事がコア業務にシフトする秘訣と成功例

労務コラム2019.04.24RPAは万能なのか?~人事が「RPA」を正しく理解するために~

労務コラム2019.03.26なぜ、人事労務業務をアウトソースしてもコスト削減が進まないのか?


求める人物像とは、会社の経営・成果創出に必要な人物の採用基準となる人物要件を設定し、採用計画や情報発信、そして選考設計に活かしていくもの



選考プロセス設計とは、求める人物像で設定した要素を「評価項目」に落とし込み、その評価項目を見極めることができる「選考手法」を決定して、「選考手法の順番」を組み立てることです。

説明会は、企業と学生が対面する重要なイベントです。
説明会を効果的に運営する為には、プログラム内容やコンテンツだけではなく、「プレゼンターの演出」でその効果を高めることができます。

選考詳細設計とは、評価項目を見極めるために、各選考手法での評価方式や質問内容/ディスカッションテーマを決定し、選考運営を円滑に進めるための評定票やタイムテーブルを策定することです。


内定フォローとは、内定者に対して、内定出しから入社式を迎えるまでの期間、
自社へのモチベーションの維持・向上に繋げるアクションのことです。
